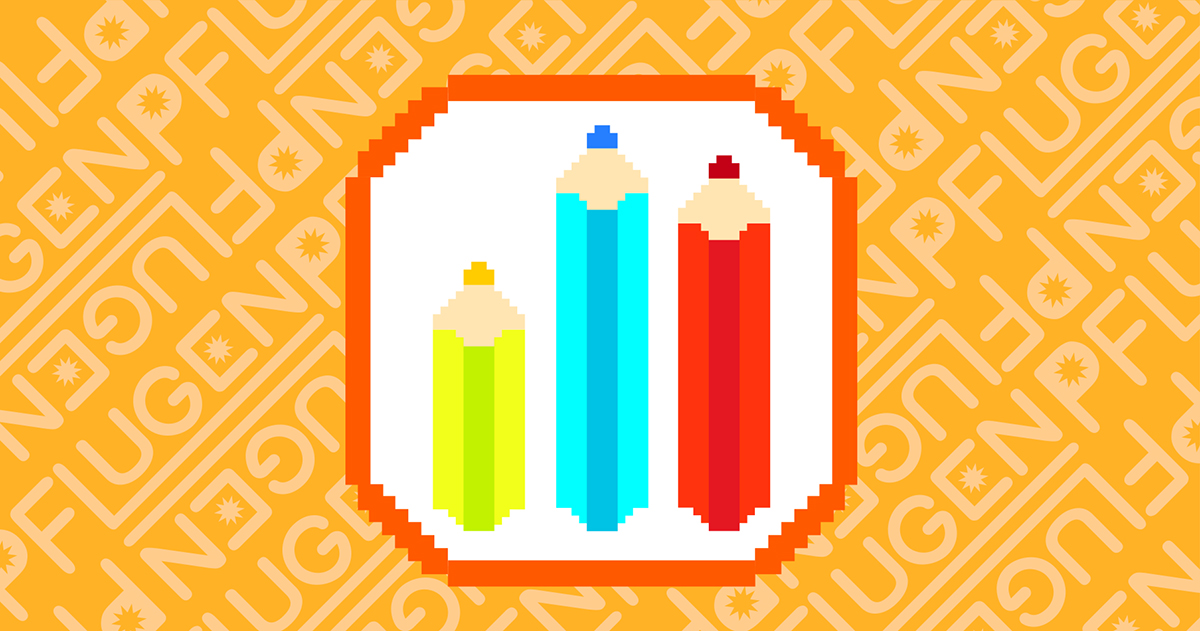はじめに
これまで、2 回ほどブログで物語に関して述べましたが、今回はなぜ人がコンテンツなどで物語を求めて いるのかについて述べてみたいと思います。
仕事がら web 記事の中で消費者行動に関することなどを目にしています。
消費者の行動データを見ていると広告宣伝媒体のコンテンツに関しては、若い消費者には物語性があった 方が馴染むとしています。
日本経済新聞の 6 月 30 日の記事の中で、自動車産業 9 社の株価よりも音楽・ゲームを含めたエンターテ インメント業界 9 社の株価が上まわり逆転したとされていました。
また、7 月 28 日新聞のオンライン記事で「アニメ鬼滅の刃」劇場版新作の興業収入が 100 憶円突破したと 説明しています。
そのような記事から見ても人はエンターテインメント(物語的なコンテンツ)を求めていることが分かり ます。
若かろうが、歳をとっていようが、人は生きている限りエンタメ性なるものを求めていきます。
エンタメのコンテンツに対して、絵画や小説、流行歌などをふくめてクリエイターの訴えたい内容は余ほ どのことがない限りほとんどが物語性をおびています。
なぜ、人がエンタメに於けるコンテンツ求めているかについて私なりに考えてお話します。
なぜ、人はエンタメが必要か
2013 年 2 月 20 日の日経新聞の記事に「涙活」の記事が載っています。
今から 12 年ほど前の「涙活」に関しては、当時マスコミなどで一時話題になっていました。
「涙活」を簡単に述べるとエンタメのコンテンツなどで、ストレスを涙を流すによって洗い流して、日々の活力を取り戻すための行動のことを意味しています。
また、最近の出版物でいえば、タイトルが「泣く消費」という本があります。
この本には、なぜ人は悲しいものが必要になるのかなどについて述べられています。
先ほども述べたように私が考えると「涙活」の話題や「泣く消費」の本などに述べられていることは、生きて 行くために人は感動や共感などをエンタメのコンテンツに求めていることは、必然的なことだと思います。
私が調べて行く中で理解したのは、人の進化の過程から顧みても人は生きているいる限り、できれば親し い人も一緒に泣いて笑い、分かち合い思いを共有したいと思うのは自然だと考えます。
それらに関していえば、Z 世代などの間で使われている Instagram や TikTok などのデジタルコンテンツの ツールなどは、友人や仲間たちと自分の感動や思いなどを共有したいという思いに添って使われていると 考えます。
このように SNS の世界では、自分の周りで現実に起きたことや音楽やアニメなどの話題そのものが経済の 大きなトレンドの要素なっています。
特に近年では、いち早く話題になっているコンテンツ情報を友人や仲間たちに知らせて共有したいと思う 人が日本の中でも多くみかけるようになってきたと考えます。
なぜ、人はコンテンツで感動するのか
あなたも私も映画やテレビドラマのヒーローやヒロインが悪党によって責められて、危険が迫り窮地にさらされて いるのを見た時に実体験のように、あなたも私もワクワクやドキドキしながら没入できている理由は、脳にあるミラーニューロン存在があるからです。
ミラーニューロンについては以前のブログでも書いたと思いますが、改めて述べるとミラーニューロンという細胞が発見されたのは今から約 30 年ほど前、1996 年にイタリアの神経生理学者のジャコモ・リゾッティ博士たち がサルを使い神経反応活動の実験で偶然に見つかった出来事です。
ジャコモ・リゾッティ博士たちがアイスクリームを食べているところをサルが見ており、サルの脳が反応している ことが分かり、サルが食事をしていた時に反応した脳の部位が同じだったことでミラーニューロンの存在が分かりました。
仮にタレントがテレビの中で食事をしているところ見ると人もサルも同じようにミラーニューロンが働きます。

先ほど述べたように映画やテレビドラマの中で、ヒーローやヒロインが悪党に襲われていれば、あなたも私もヒ ーローやヒロインと同じような気持ちになりドキドキハラハラしてしまいます。
最後にヒーローとヒロインは、悪党を懲らしめることによって、見ているあなたも私も気持ちがスカッとし感動を します。
あなたも分かっているようにそれは、あくまでもバーチャルな疑似体験であって、あなたや私の現実世界で起き ているワケではありません。
よくあるような青春恋愛ドラマでヒーローやヒロインが大ケガや病気によって亡くなる場面などは観ている人々の 涙を誘います。
このように人が、先ほどの涙活や泣ける消費でも述べられているように本能的に擬似的な体験を求める傾向が あるようです。
また、人が遊園地のおばけ屋敷やホラー映画を求める傾向も怖いものに出会って恐怖を感じる体験により、精 神を開放することで日頃たまったストレスが発散できることは、涙活との違いがあっても精神的な作用としては、 ストレス解消に関しては同じことと捉えることができると思われます。
コンテンツマーケティングにとって感動と共感が重要な時代
昔から人には当然のように感動と共感が必要なるのは同じなのですが、消費に関してマーケティングの視点から 顧みると、特にコンテンツ制作に関して消費者に感動を呼び起こし共感させることが、消費力に影響し大切だと 過去の流れをみれば理解ができます。
消費者の消費行動から顧みると、1970 年代は、まだ大衆がモノを求めていたモノ消費時代でした。
その後 1980 年代には大衆にモノが揃ってきて、1990 年代ににはモノ消費からコト消費の時代に入りました。
その後 2010 年代に入るとトキ消費になり、2020 年代にはイミ消費になり、今後の消費者の消費活動には、 エモーショナル(感情的)活動の傾向が強くなると予想されます。
消費者の消費行動サイクルは 2013 年に話題となった「涙活」をはじめ、今後いっそう老若男女併せて消費者は、 エモーショナルな消費活動につながって行くと思われます。
出典:2005 年 12 月 20 日 .(刊)株式会社祥伝社 .(著)渡邊憲一 .(原案)株式会社テレビ朝日 .「ジュ ラシックコード」・日本経済新聞 :2025 年 6 月 30 日 19:28(記事 / 編集)越智小夏・今堀祥和「時価総額、 エンタメが自動車抜く上位 9 社で見えた日本株高の原動力」・読売新聞社オンライン 2025/07/28 13:05.「鬼滅の刃」無限城編、興行収入100億円突破...無限列車編より2日早く国内最速更新」・フリー百科 , Wikipedia.「涙活」・日本経済新聞 .2013 年 2 月 20 日 6:30.[nikkei WOMAN Online 2013 年 2 月 18 日掲 載 ].(文)西尾英子 .「ストレスから解放 自ら泣いて心を癒やす「涙活」とは」・2023 年 6 月 2 日(刊)株 式会社クロスメディアパブリシング .(著)今龍健登 .「エモ消費 世代を超えたヒットのルール」・2015 年 11 月 5 日 .(刊)株式会社新星出版社 .(監修)池谷裕二「大人のための図鑑 ビジュアル版 脳と心のしくみ」
今回もデザインとマーケティングにお付き合い頂き、誠にありがとうございました。
今後もデザインとマーケティングを宜しくお願い致します。
文 / デザイン・マーケティング担当 太田正信